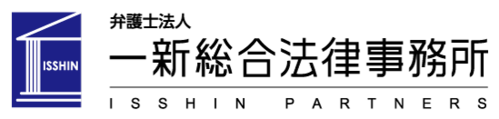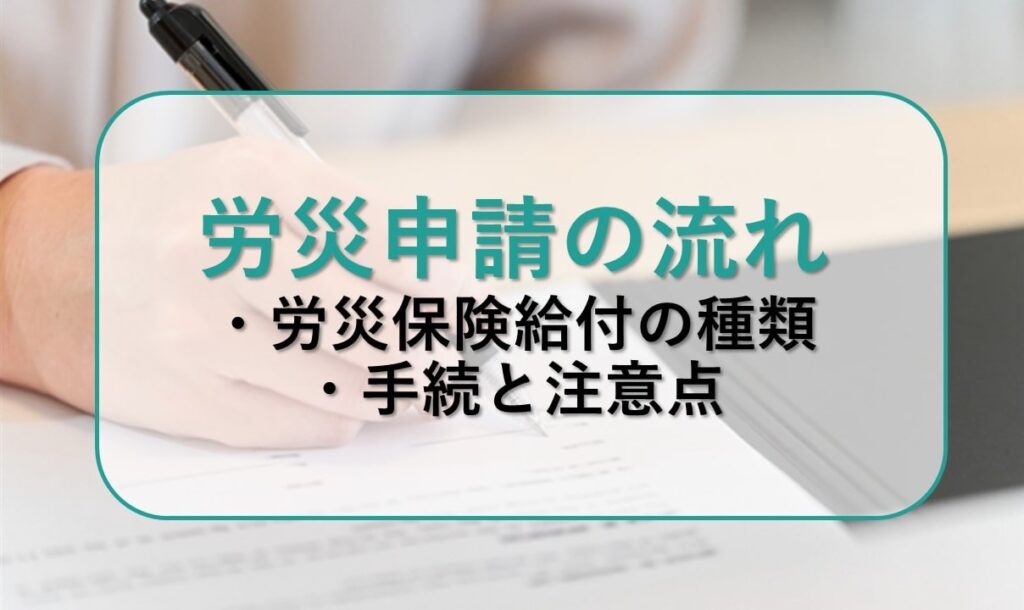
業務中または通勤中の事故等でケガをしたときや、業務に起因して病気になったときには、労災保険により一定の補償を受けることができます。
本記事では、基本的な労災認定を受けるための申請の流れと注意点について解説します。
- 1. 労災申請の流れ
- 1.1. 労働災害が発生したことを会社に報告する
- 1.2. 医療機関に行って医師の診察を受ける
- 1.3. 労働基準監督署へ労災保険給付の申請を行う
- 1.4. 労働基準監督署による調査と支給・不支給の決定
- 2. 主な労災保険給付の種類と申請の際に必要な書類をご紹介
- 2.1. 療養(補償)給付
- 2.2. 休業(補償)給付
- 2.3. 障害(補償)給付
- 2.4. 遺族(補償)給付
- 2.5. 葬祭料・葬祭給付
- 2.6. 傷病(補償)年金
- 2.7. 介護(補償)給付
- 3. 労災申請時に発生しがちなトラブルとは?
- 3.1. 会社が労災保険の加入手続行っていない
- 3.2. 会社が労災申請に協力してくれない
- 3.3. 労災申請の時効を過ぎてしまった
- 4. まとめ
労災申請の流れ
労災保険の給付を受けるまでの流れについてご説明します。
▼労働災害が発生したことを会社に報告する
▼医療機関で医師の診察を受ける
▼労働基準監督署へ労災保険給付の申請を行う
▼労働基準監督署による調査と支給・不支給の決定
労働災害が発生したことを会社に報告する
仕事中や通勤中の事故等で負傷した場合は、まずは会社に報告をしましょう。
労災の認定を得るためには事業主の証明など勤務先(会社)の協力が必要になります。
また、事業主は労災の発生を労基署に報告する義務がありますので、被災労働者はいつどこでどのような事故があったのか、詳細を勤務先(会社)に伝えましょう。
重傷・死亡事故でご本人が会社に連絡することが難しい場合には、ご家族等からお伝えいただくことになります。
医療機関に行って医師の診察を受ける
労災事故にあったら早めに医療機関を受診しましょう。
適切な補償を受けるという観点からも、早めに医師の診察を受けて労災事故発生直後の怪我の状態を記録に残しておくことは、重要なポイントとなります。
【受診する医療機関について】
労災保険指定医療機関で治療を受けた場合、労災に認定されると治療費は医療機関に対して直接支払われます。
なお、労災保険指定医療機関で治療を受けた場合には、当該医療機関に後述の療養(補償)給付の申請書類を提出して、治療費に関する労災保険給付の手続を行うことができます。
一方、労災保険指定医療機関以外で治療を受けた場合には、被災者が治療費を窓口で一旦支払う必要が生じます。
労災事故では健康保険を利用できないため、場合によっては高額の治療費となることもあります。
したがって、労災によるケガ等で受診をされる際は、なるべく労災保険指定医療機関で治療を受けるのがよいでしょう。
労働基準監督署へ労災保険給付の申請を行う
労災保険給付には様々な種類がありますが、いずれも労働基準監督署に申請書類を提出して申請を行うという点は共通しています。
請求のタイミングは、労災保険給付種類によって異なります(詳しくは後述します)。
診察・治療が一段落したら、申請書類を作成し、所轄の労働基準監督署に労災保険給付の申請を行いましょう。
提出する書類は、給付の種類によって書式が決まっています。
厚生労働省のホームページに労災保険給付の申請書の一覧があるので、ご自身が対象となる給付の種類を確認したうえで、必要な労災保険給付の申請書の作成を行いましょう。
なお、労災保険給付の申請は、会社が手続を代行してくれることもありますので、具体的な申請手続については会社と相談して進めるようにしてください。
申請書には事業主の証明欄があり、勤務先に記入してもらう必要があります。
また、休業(補償)給付を申請するにあたっては、事業主の証明に加えて診療担当者の証明が必要となります。
※労災保険給付の種類ごとに提出が必要な書類については後述します。
※勤務先が労災保険の申請に協力してくれない場合については後述します。
労働基準監督署による調査と支給・不支給の決定
申請書等を提出すると、労働基準監督署が労災事故について調査し、支給・不支給の決定をします。
主な労災保険給付の種類と申請の際に必要な書類をご紹介

それぞれの補償内容と、請求する際に記入が必要な書類について解説をします。
療養(補償)給付
労災による傷病の診療費用や薬剤支給、治療、手術、入院、移送などの費用の給付です。
業務災害と通勤災害、そして被災労働者が治療を受けた病院が労災保険指定医療機関に該当するかどうかによって、請求用紙が異なります。
【指定医療機関を受診した場合】
・業務災害:「療養補償たる療養の給付請求書(様式第5号)」
・通勤災害:「療養給付たる療養の給付請求書 通勤災害用(様式第16号の3)」
【指定医療機関以外を受診した場合】
・業務災害:「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」
・通勤災害:「療養給付たる療養の費用請求書 通勤災害用(様式第16号の5)」
指定医療機関であれば指定医療機関を経由して労働基準監督署に書類を提出することになりますので、書類の提出先は指定医療機関となります。
指定医療機関以外の場合は労働基準監督署に書類の提出を行ってください。
休業(補償)給付
労災による傷病により休業した場合に支給される補償です。
具体的には、①業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため、②労働することができないため、③賃金を受けていない、という3要件を満たす場合に、その第4日目から、休業(補償)等給付と休業特別支給金が支給されます。
休業(補償)給付を受けるには医師の証明が必要となります。
・業務災害:「休業補償給付支給請求書 業務災害用(様式第8号)」
・通勤災害:「休業給付支給請求書 通勤災害用(様式16号の6)」
障害(補償)給付
労災による傷病が治ゆ(傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態)と診断された後、一定の残存障害が認められる場合に支給される補償です。
残存障害が、障害等級表(省略)に掲げる障害等級に該当するとき、その障害の程度に応じて、それぞれ以下のとおり支給されます。
障害等級第1級から第7級に該当するとき:障害(補償)等年金、障害特別支給金、障害特別年金
障害等級第8級から第14級に該当するとき:障害(補償)等一時金、障害特別支給金、障害特別一時金
・業務災害:障害補償給付支給請求書(様式第10号)
・通勤災害:障害給付支給請求書(様式第16号の7)
請求する際は医師の診断が必要となります。
申請書類には医師が作成した労災の書式の後遺障害診断書等の資料もあわせて添付し提出します。
・診断書書式>>https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001076661.pdf
審査の結果、障害認定がなされる場合には、支払決定通知が送付され等級に応じた保険給付がなされます。
一方、等級認定が受けられなかった場合には、不支給決定通知が送付されます。
労災の障害(補償)給付の申請に関しては、以下の記事で詳しく解説しております。
遺族(補償)給付
労災によって労働者が亡くなった場合に、遺族に対して支給される補償です。
遺族(補償)等年金の受給資格者となるのは、被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
なお、妻以外の遺族については、被災労働者の死亡の当時に一定の高齢または年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要となります。
遺族(保証)給付には、主に遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。
・遺族(補償)年金を請求する場合:「遺族補償年金支給請求書」または「遺族年金支給請求書」
添付書類(死亡診断書や死体検案書、戸籍謄本、被災労働者の収入により生計を維持していたことの証明資料など)と一緒に労働基準監督署長に提出します。
・遺族(補償)一時金を請求する場合:「遺族補償一時金請求書」または「遺族一時金支給請求書」
提出の際には、各ケースに応じた添付書類の提出も必要となります。
葬祭料・葬祭給付
労災によって亡くなった労働者の葬祭を執り行う遺族等に対して、支給される保証です。
葬祭料等(葬祭給付)の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。
この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分が支給額となります(令和6年2月現在)。
・業務災害:葬祭料請求書(様式第16号)
・通勤災害:葬祭給付請求書(様式第16号の10)
申請にあたっては、被災労働者が死亡したことを明らかにするための除籍謄本や住民票などが必要となります。
傷病(補償)年金
労災によって療養(補償)給付を受けている労働者が、療養開始から1年6か月経っても治らない場合、傷病等級に応じて支給されます。
傷病(補償)年金の支給・不支給の決定は、所轄の労働基準監督署長の職権によって行われるため、被災労働者が申請手続きをする必要はありません。
介護(補償)給付
労災によって療養(補償)給付を受けている労働者に、一定の障害があり、介護を必要とする場合に支給される補償です。
・介護補償給付支給請求書(様式第16号2の2)
介護に要した費用の額の証明書や、診断書の提出も必要となります。
労災申請時に発生しがちなトラブルとは?

労災申請をする際によくあるトラブルについて解説します。
会社が労災保険の加入手続行っていない
パート、アルバイトを含めた労働者を1日1人でも雇っていれば、労災保険の加入は事業主の義務となります(※)。
中には労災保険への加入手続を行っていない会社も存在しますが、万が一、勤務先の会社が労災保険の加入手続を怠っていたとしても、労働基準監督署に対して労働災害発生の事実を申告して労災申請の手続きを行い、労災認定を受けられれば、通常どおり各種労災保険の給付を受けることが可能です。
※5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産事業を除く
会社が労災申請に協力してくれない
会社が労働災害の発生の事実が公になることを恐れ、、労災保険給付の申請手続き等に協力してくれないケースがあります(いわゆる労災隠し)。
会社の協力が得られない場合は、会社が事業主の証明に協力してくれないことを労働基準監督署に相談したうえで、直接労災申請を行いましょう。
必要書類は、労働基準監督署でも教えてくれますが、ご自身での手続きが難しいようであれば、弁護士などの専門家のサポートを受けることをおすすめします。
労災申請の時効を過ぎてしまった
労災申請には、時効があり、時効期間が過ぎてしまうと給付が受けられなくなってしまいます。
時効期間は給付の種類ごとに異なるため注意が必要です。
【労災保険給付の種類と申請期限】
| 保険給付 | 期間 | 起算点 |
| 療養(補償)給付 | 2年 | 療養の費用を支払った日ごとにその翌日休業の日ごとにその翌日 |
| 休業(補償)給付 | 2年 | 休業の日ごとにその翌日 |
| 障害(補償)給付 | 5年 | 傷病が治癒した日の翌日 |
| 遺族(補償)給付 | 5年 | 労働者が死亡した日の翌日 |
| 葬祭料(葬祭給付) | 2年 | 労働者が死亡した日の翌日 |
| 介護(補償)給付 | 2年 | 介護を受けた月の翌月の初日 |
まとめ
労災申請に必要な書類は、申請書の種類だけでも多数あり、その他の証拠となる添付書類、医師の証明など多岐にわたります。
労働基準監督署に提出する申請書類をきちんと準備することが、労災認定を得るための重要なポイントであると言えます。
勤務先(会社)が労災の申請に協力的ではない、申請書類を準備することにも不安、負担が大きいという方は、早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。
一新総合法律事務所では、労災被害にあわれた方やそのご家族が適切な補償を会社から受けるためのサポートを行っております。
事案によっては、労災保険ではカバーされない慰謝料の請求や、後遺障害を負った場合の収入補償(逸失利益)の請求などが可能なケースもあります。
お気軽にご相談ください。
※本記事は2024年2月時点の法律をもとに執筆しています。